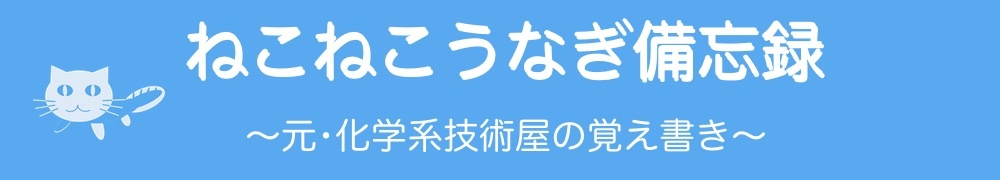熱力学の第一法則で出てくる内部エネルギーですが、その中身について整理しました。
目次
内部エネルギーは、系の内部に保持される熱力学的なエネルギーで、示量性の状態量です。
といってもピンときませんが、その実体は「系の物質の分子の持つエネルギーの総和」です。マクロな熱力学の世界からではなく、ミクロの気体分子運動論の世界から導出されます。
単原子分子の理想気体について考えます。
一片の長さLの立方体の断熱容器のなかに、質量mの気体分子がN個入っているとします。
分子の運動のx方向の成分のみに着目して考えると、
1分子が壁に1回衝突する際に壁から受ける力積(= 運動量の変化 = Δ(質量 × 速度) )は
(衝突後の運動量) − (衝突前の運動量) なので \( \scriptsize (-mv_x) – (mv_x) = -2mv_x \)
衝突は弾性衝突(壁にエネルギーを吸収されない)を前提に考えるので、
作用反作用の法則より
1分子が壁に与える力積は \( \scriptsize 2mv_x \)
1分子が時間Δtの間に衝突する回数は(壁までの往復距離が2Lなので) \( \small \frac{v_x \Delta t}{2L} \)
よって、1分子がΔtの間に壁に与える力積の総和は
\( \scriptsize 2mv_x \times\small \frac{v_x \Delta t}{2L} \scriptsize= \small\frac{mv_x^2}{L}\scriptsize\Delta t \)
1分子が平均的に壁に与える力は、(力積 = 力 ✕ 時間 から)力積を時間で割って
\( \small\frac{mv_x^2}{L}\scriptsize\Delta t / \Delta t = \small\frac{mv_x^2}{L} \)
ここでx方向だけでなくx,y,z全方向と運動方向の速度成分について考えると
\( \scriptsize v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2 \)
平均について(※反対方向どうしの動きで打ち消し合うのを防ぐため二乗の平均で考え)
\( \scriptsize \bar{v^2} = \bar{v_x^2} + \bar{v_y^2} + \bar{v_z^2} \)
気体の圧力は全方向同じなので、速度二乗の平均も全方向等しく\( \tiny \bar{v_x^2} = \bar{v_y^2} = \bar{v_z^2} \)
\( \scriptsize \bar{v^2} = 3 \bar{v_x^2} \) ⇒ \( \scriptsize \bar{v_x^2} = \frac{1}{3} \bar{v^2} \)
N個の分子が壁に与える平均の力は
\( \small\frac{m\bar{v_x^2}}{L} \scriptsize \times N = \small\frac{m\frac{1}{3}\bar{v^2}N}{L} \scriptsize = \small\frac{m\bar{v^2 }N}{3L} \)
よって、壁にかかる圧力は
\(\scriptsize P = \small\frac{m\bar{v^2 }N}{3L} / \scriptsize {L^2} = \small\frac{m\bar{v^2 }N}{3L^3} \scriptsize = \small\frac{m\bar{v^2 }N}{3V}\)
理想気体の状態方程式 \(\scriptsize PV=nRT \) から
\( \small\frac{m\bar{v^2 }N}{3} \scriptsize= nRT =\frac{N}{N_A}RT \)
絶対温度 T[K] の単原子分子の理想気体一個当たりが持つ運動エネルギー μ[J] は、
ボルツマン定数 \(\scriptsize k_B=\frac{R}{N_A} \)を用いて
\(\scriptsize \mu = \frac{1}{2} m \bar{v^2} = \frac{3}{2} k_B T \)
n [mol] の気体分子の個数は n・NA 個なので、
単原子分子からなる理想気体 n mol における内部エネルギーU は
\(\scriptsize \color{red}{U }= (nN_A ) \cdot \frac{3}{2} k_B T \)
\(\scriptsize = (nN_A ) \cdot \frac{3}{2} \frac{R}{N_A} T \)
\(\scriptsize \color{red}{= \frac{3}{2} nRT} \)
2原子分子の場合は、これに回転運動が加わることから
\(\scriptsize \color{red}{U = \frac{5}{2} nRT} \)
内部エネルギーの変化は、全微分の形で次のように表されます。
\( \scriptsize dU= \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_{V} dT + \left( \frac{\partial U}{\partial V} \right)_{T} dV \)
熱力学第一法則より、系が微小変化したときの内部エネルギー変化は
\( \scriptsize dU= \delta Q + \delta W = \delta Q – pdV \) (微小区間なのでpは一定とみなします)
したがって
\( \scriptsize \delta Q = \left\{ \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_{V} dT + \left( \frac{\partial U}{\partial V} \right)_{T} dV \right\} + pdV \)
\( \scriptsize = \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_{V} dT + \left\{ \left( \frac{\partial U}{\partial V} \right)_{T} + p \right\}dV \)
定積変化の場合は dV=0 となるため
\( \scriptsize (\delta Q)_V = \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_{V} dT \) ∴ \( \scriptsize \frac{ (\delta Q)_V}{dT} = \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_{V} \)
これは、等積変化において物質を1K温度上昇させるのに必要な熱量を示し、
定積熱容量といいます。
\( \scriptsize \color{red}{C_V = \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_V} \)
したがって、ある温度区間の変化に対して、内部エネルギーの変化は
\( \scriptsize\color{red}{\Delta U = C_V \Delta T} \)
ところで、単原子分子の理想気体の内部エネルギーは \(\scriptsize U = \frac{3}{2} nRT \) だったので
\(\scriptsize \Delta U = \frac{3}{2} nR \Delta T = C_V \Delta T \)
\(\scriptsize \color{red}{C_V=\frac{3}{2} nR} \)
1 mol あたりの熱容量は
\(\scriptsize \color{red}{\frac{C_V}{n}=\frac{3}{2} R} \)
で、これを定積モル比熱といいます(※定積モル比熱の記号を CV とする場合もあります)。
ところで、「体積一定の条件以外でも、定積熱容量CVは内部エネルギー変化の式 ΔU = CVΔT に使うことができるのか」という疑問に引っかかってしまうことがあると思います。結論からいうと「定積以外でも ΔU = CVΔT は成立します」。たとえば、定圧条件下でも成立します。
上にも出てきましたが、内部エネルギーの変化は、全微分の形で
\( \scriptsize dU= \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_{V} dT + \left( \frac{\partial U}{\partial V} \right)_{T} dV \)
となりますが、この式は体積一定の条件でなくとも常に成立します。
また実は、この式の \( \tiny \left( \frac{\partial U}{\partial V} \right)_{T} \)は、
ジュールの自由膨張の実験結果 から「内部エネルギーは体積変化の影響をうけない」ので
\( \tiny \left( \frac{\partial U}{\partial V} \right)_{T} =0 \) となり
\( \scriptsize dU= \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_{V} dT \) つまり \( \scriptsize \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_{V} = \frac{dU}{dT}\)
であるので、定積熱容量は、体積一定かどうかに関わらず、内部エネルギーを温度で微分したものに相当することがわかります。
\( \scriptsize C_V = \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_{V} = \frac{dU}{dT}\)
いいかえると、ΔU = CVΔT は定積条件かどうかに関わらずに成立します。
なお当然ですが、熱容量としてのCVは定積条件下であることが前提です。定圧と定積の条件下では、それぞれ熱容量(あるいはモル比熱)は異なります。
次に定圧条件下での熱容量を示しますが、もし定圧条件下でCVを使おうとすると補正の項が必要になります。
体積V について全微分は
\( \scriptsize dV= \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_{p} dT + \left( \frac{\partial V}{\partial p} \right)_{T} dp \)
定積変化の場合は dp=0 となるため
\( \scriptsize dV= \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_{p} dT \)
系が微小変化したときの内部エネルギー変化は
\( \scriptsize \delta Q = \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_{V} dT + \left\{ \left( \frac{\partial U}{\partial V} \right)_{T} + p \right\}dV \)
\( \scriptsize (\delta Q)_p = \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_{V} dT + \left\{ \left( \frac{\partial U}{\partial V} \right)_{T} + p \right\} \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_{p} dT \)
\( \scriptsize = \left[ \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_{V} + \left\{ \left( \frac{\partial U}{\partial V} \right)_{T} + p \right\} \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_{p} \right] dT \)
よって
\( \scriptsize \frac{(\delta Q)_p}{dT} = \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_{V} + \left\{ \left( \frac{\partial U}{\partial V} \right)_{T} + p \right\} \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_{p} \)
となり、等圧変化において物質を1K温度上昇させるのに必要な熱量を示し、
定圧熱容量といいます。
\( \scriptsize \color{red}{ C_p = \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_{V} + \left\{ \left( \frac{\partial U}{\partial V} \right)_{T} + p \right\} \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_{p} } \)
1 mol あたりの熱容量 \(\scriptsize \color{red}{\frac{C_p}{n} } \) を定圧モル比熱といいます。
(※定圧モル比熱の記号を Cp とする場合もあります)
ここで ジュールの自由膨張の実験結果 から\( \tiny \left( \frac{\partial U}{\partial V} \right)_{T} =0 \) であり、また 定積熱容量 \( \tiny C_V = \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \) から
\( \scriptsize C_p = C_V + p \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_{p} \)
さらに 理想気体の状態方程式から \( \tiny \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_{p} =n\frac{R}{p} \) となるため、
\( \scriptsize C_p= C_V + nR \) すなわち \( \small\color{red}{ \frac{C_p}{n} – \frac{C_V}{n} \scriptsize= R } \)
となって
マイヤーの関係式(定圧モル比熱と定積モル比熱の差が気体定数Rとなる)が得られます。
導出の過程の式からわかるように、定圧熱容量と定積熱容量の差 \( \tiny p\left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_{p} \) は、外圧に対する体積変化の仕事分に相当する熱容量に該当します。いいかえると、定圧下で気体の温度を上げようとすると、定積熱容量から求まる熱量に加えて、体積変化の仕事分のエネルギー(熱量)が必要になる、ということです。
また導出において、定圧熱容量およびマイヤーの関係の式は、気体分子が単原子分子か2原子分子かどうかを前提条件にしていません。したがって、単原子分子であろうとも2原子分子であろうとも、これらの式は成立します。